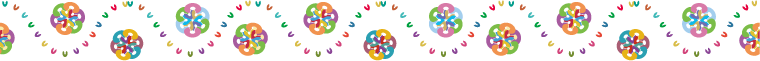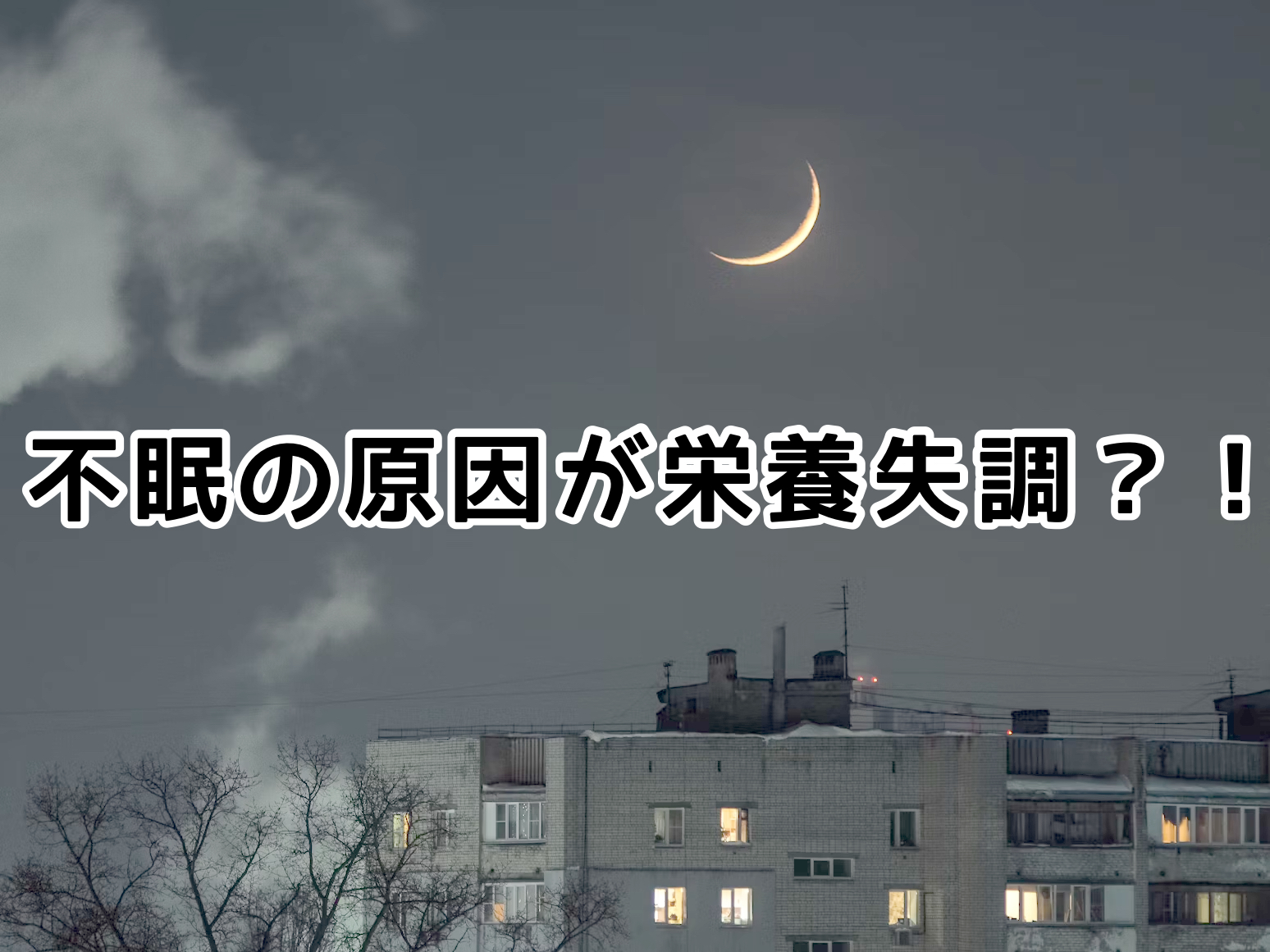こんにちは!あなたの健康と美容を応援するAyuです😊
「ベッドに入っても、目が冴えてしまって眠れない…」
「夜中に何度も目が覚めて、朝にはぐったり…」
「明日も仕事なのに…と焦れば焦るほど、眠れなくなる…」
そんな、出口の見えない「不眠」のループに、苦しんでいませんか?
眠れない夜のツラさ、そして翌日の心と体への影響は、経験した人にしか分からない、本当に深刻な悩みですよね。
睡眠薬に頼るのも一つの方法ですが、「できれば薬は使いたくない」「根本的な解決策が知りたい」と感じている方も多いはず。
もし、そのつらい不眠が、あなたの心の問題ではなく、体の“栄養不足”が原因だとしたら…?
今回は、そんな不眠を改善するための「栄養学」にスポットライトを当てます。
-
そもそも、なぜ栄養で不眠が改善するの?
-
ぐっすり眠るための“睡眠ホルモン”とその材料
-
脳の興奮を鎮め、リラックスに導く成分とは?
この記事を読めば、科学的根拠に基づいた、薬に頼らない新しいアプローチを手に入れることができます。
もう、眠れない夜に一人で悩まないで。栄養の力で、穏やかな眠りを取り戻しましょう。
![]()
▼日中のストレスやイライラも、不眠の大きな原因です。また、不眠が原因でイライラしてしまうことも。
心のケアのための栄養学については、こちらの記事もぜひ参考にしてくださいね。

![]()
不眠と栄養の深い関係|なぜ食べたもので眠りが変わるのか?
「夜、自然に眠くなり、朝、スッキリと目が覚める」
この当たり前のようなリズムは、私たちの脳内で働く「神経伝達物質」や「ホルモン」の絶妙な連携プレーによって成り立っています。
そして、これらの物質は、決してゼロから生まれるわけではありません。
すべては、私たちが口にした食べ物に含まれる「栄養」を材料として作られているのです。
つまり、
-
日中の活動モードを司るホルモン(交感神経を優位にする)
-
夜のリラックスモードを司るホルモン(副交感神経を優位にする)
これらの材料となる栄養が不足していては、体内時計はうまく機能せず、夜になっても脳が興奮したまま。その結果、不眠という深刻な状態に陥ってしまうのです。
「眠れない」のは、あなたのせいではなく、単純に脳の“栄養失調”が原因かもしれないのです。
【睡眠ホルモン】メラトニンの材料と、その合成チーム
つらい不眠を改善し、深い眠りへといざなう、最も重要なホルモン。
それが、「メラトニン」です。
メラトニンは、夜になると脳の松果体という部分から分泌され、体温や血圧を下げて、心と体を自然な眠りに導きます。別名「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。
このメラトニンは、一体何から作られるのでしょうか?
その製造工程を見てみましょう。
【メラトニン製造工場】
① 材料の搬入:トリプトファン
まず、必須アミノ酸の一種である「トリプトファン」が、食事から体内に取り込まれます。これが、すべての始まりとなる“大元の材料”です。② 第一工程:セロトニンへの変換
昼間、太陽の光を浴びると、トリプトファンは「幸せホルモン」である「セロトニン」に変換されます。この時、職人としてビタミンB6、ナイアシン、葉酸、鉄、マグネシウムが必要です。日中の心の安定は、このセロトニンによって保たれます。③ 最終工程:メラトニンへの変換
夜になり、周囲が暗くなると、昼間に作られたセロトニンを材料にして、最終製品である「メラトニン」が合成されます。この時も、職人としてビタミンB6やマグネシウムが活躍します。
この工程、驚くほど精巧ですよね!
ポイントは、夜のメラトニンは、昼間のセロトニンから作られるということ。
つまり、不眠を改善するには、夜だけでなく、日中の過ごし方と栄養摂取が非常に重要なのです。
【もっと詳しく! ビタミンB群編】
このように、ビタミンB群は、心の安定にも深く関わっています。「チームで働く」ビタミンB群の基本については、こちらの記事で詳しく解説しています。
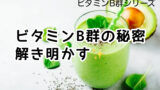
【もっと詳しく! 鉄分編】
女性に特に多い「隠れ貧血」と、鉄分サプリが効かない意外な原因については、こちらの記事で詳しく解説しています。

不眠改善のための栄養素①:トリプトファン
まずは、大元の材料であるトリプトファンをしっかり摂ることがスタートラインです。
トリプトファンは体内では作れない「必須アミノ酸」なので、食事から補給する必要があります。
【トリプトファンが豊富な食材】
-
乳製品:牛乳、チーズ、ヨーグルト(特にホットミルクは有名ですね)
-
大豆製品:豆腐、納豆、味噌
-
その他:バナナ、ナッツ類、赤身肉、魚、卵
不眠改善のための栄養素②:ビタミンB群(特にB6)
ビタミンB6は、トリプトファン→セロトニン、セロトニン→メラトニンという、2段階の変換プロセス両方で活躍する、超重要な職人です。
ビタミンB6がなければ、いくら材料があっても、幸せホルモンも睡眠ホルモンも作られず、不眠は改善されません。
【ビタミンB6が豊富な食材】
-
かつお、まぐろ、さけなどの魚類
-
鶏肉、レバー
-
バナナ、パプリカ、さつまいも
【脳の興奮を鎮める】リラックス成分「GABA」の力
「ベッドに入っても、仕事のことや明日のことで頭がいっぱい…」
そんな、思考がぐるぐるして眠れないタイプの不眠には、脳の興奮を鎮めてくれる「GABA(ギャバ)」が助けになります。
GABAは、アミノ酸の一種で、神経の過剰な興奮を抑え、心と体をリラックスさせる働きがあります。
ストレスや不安で交感神経が高ぶった状態を、穏やかな副交感神経優位の状態へと切り替えてくれる、「眠りのブレーキ」のような存在です。
【もっと詳しく!】
日中のイライラや不安感が強いと、夜になっても脳の興奮は収まりません。ストレス社会で戦うあなたの心を軽くするための栄養学については、こちらの記事も、ぜひ合わせてお読みください。

GABAは体内で作ることもできますが、食事やサプリメントから補うことも有効です。
【GABAが豊富な食材】
-
発芽玄米、トマト、じゃがいも、かぼちゃ
-
漬物、キムチなどの発酵食品
薬に頼らない!不眠を改善する、5つの夜の習慣
これらの栄養ケアと合わせて、夜の過ごし方を見直すことで、不眠の改善効果は劇的に高まります。
-
夕食は寝る3時間前までに
寝る直前に食事をすると、消化活動で内臓が休まらず、眠りが浅くなります。 -
夜はカフェイン・アルコールを控える
カフェインの覚醒作用は3〜4時間続きます。アルコールは寝つきを良くするかもしれませんが、利尿作用や中途覚醒の原因となり、結果的に不眠を悪化させます。 -
ぬるめの入浴でリラックス
寝る1〜2時間前に、38〜40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かると、心身がリラックスし、その後の体温低下とともに自然な眠気が訪れます。 -
寝る1時間前はデジタルデトックス
スマホやPCのブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を強力に抑制します。寝室にはスマホを持ち込まない、と決めるのがおすすめです。 -
朝、太陽の光を浴びる
夜の習慣ではありませんが、これが一番重要かもしれません。朝、太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が始まります。これが、夜の質の良い眠りに繋がり、不眠の根本的な改善に繋がるのです。
【もっと詳しく!】
このように、健康的な体を作るためには、様々な生活習慣の見直しが大切です。私が人生を変えた「5つの健康習慣」については、こちらの記事で詳しくお話ししています。

まとめ:最高の朝は、昨日の“栄養”で決まる
つらい不眠を改善するための栄養学、いかがでしたか?
「眠れない」という悩みが、いかに日中の栄養摂取と密接に関わっているか、ご理解いただけたのではないでしょうか。
-
✅ 不眠の大きな原因は、脳の“栄養失調”による、睡眠ホルモン不足。
-
✅ 睡眠ホルモン「メラトニン」の材料は、「トリプトファン」と「ビタミンB6」。
-
✅ 脳の興奮を鎮め、リラックスさせるのが「GABA」。
-
✅ 日中の過ごし方と食事が、夜の眠りの質を決定づける。
今日の夜、ぐっすり眠れるかどうかは、今日の朝・昼に何を食べたかで、すでに決まっているのかもしれません。
まずは、夕食に豆腐の味噌汁と焼き魚をプラスしてみる。
おやつにバナナやナッツを食べてみる。
そんな小さな工夫から、あなたの不眠の夜は、きっと変わり始めます。
栄養の力で、深く、心地よい眠りを取り戻し、最高の朝を迎えてくださいね。
![]()
★★★ 次回予告 ★★★
さて、質の良い睡眠で心と体の休息が取れたら、次は日中の活動を脅かす“外敵”から体を守る準備をしましょう。
特に、季節の変わり目は体調を崩しやすいですよね。
次回のテーマは、
「【免疫力アップ】風邪・感染症に負けない体を作るビタミンA, C, Dの鉄壁ディフェンス」
です!
なぜ、ある人は風邪をひきやすく、ある人はいつも元気なのか?
その差は「免疫力」にあり、そして免疫力はビタミンで強化できるんです。
ウイルスに負けない、鉄壁の体を作るための栄養学を徹底解説します。お楽しみに!
今回も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました😊