「なんだか最近、疲れやすいな…」
「冬になると、気分がどんよりする…」
「前より風邪をひきやすくなったかも?」
そんな、原因がはっきりしない“なんとなく不調”。
もしかしたら、今話題の「ビタミンD」が不足しているサインかもしれません。
こんにちは!健康と美容の情報を発信するAyuです✨
突然ですが、「現代日本人の8割が不足している」と言われる、驚異の栄養素があることをご存知ですか?
コロナ禍以降、免疫力への関心が高まったことで、ビタミンDは一躍スターダムにのし上がりました。でも、「体に良いらしい」くらいのイメージで、具体的にどんな働きをするのか、よく知らない方も多いのではないでしょうか?
このシリーズでは、そんなビタミンDの魅力を全3回にわたって徹底的に掘り下げていきます!
記念すべき第1回は【基本編】。
-
ビタミンDって、そもそも何者?
-
太陽とどういう関係があるの?
-
どうして私たちは不足しちゃうの?
こんな疑問をスッキリ解決していきます。
この記事を読み終わる頃には、あなたもビタミンD博士になっているはずですよ😉
ビタミンDは「ビタミン」ではない?驚きの正体と働きを徹底解剖
驚きの正体は「ホルモン」に近い存在だった!
「ビタミンD」という名前から、レモンのビタミンCや野菜のビタミンAのような仲間を想像しますよね。
でも実は、ビタミンDはちょっと特殊な存在。
なんと、体内で作ることができる「ホルモン」によく似た働きをするんです!
そもそも「ビタミン」の定義は、「体内で作ることができない(または十分な量を作れない)ため、食事から摂る必要がある栄養素」のこと。
でもビタミンDは、日光を浴びることで皮膚で自分で作れるんです。ユニークですよね!
体内で作られたビタミンDは、血流に乗って全身をめぐり、まるで司令塔のように体のさまざまな機能に「こうしてね!」と指令を出します。この働きぶりが、まさにホルモンそっくりなんです。
だから専門家の間では「ビタミン」というより「ホルモンD」と呼ぶべき、なんて声もあるくらいなんですよ。
骨だけじゃない!全身に関わるビタミンDのマルチな働き
「ビタミンDといえば、骨でしょ?」
そう思ったあなた、大正解です!でも、それだけじゃないのが今の常識。
ビタミンDの活躍の場は、私たちが思うよりずーっと広いんです。
-
🦴 骨の健康をサポート
カルシウムの吸収を助け、丈夫な骨や歯を作るための必須パートナー。これが一番有名な働きですね。
【もっと詳しく!】
「カルシウムだけ摂っても、骨は強くならない」という衝撃の事実、ご存知ですか?ビタミンDの最高の相棒、「ビタミンK」との連携プレーについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

-
🛡️ 免疫システムの調整役
体内に侵入してきたウイルスや細菌と戦う「免疫」をパワーアップ!風邪やインフルエンザにかかりにくい体づくりを応援します。
【もっと詳しく!】
風邪に負けない強い体を作るためには、ビタミンDだけでなく、「ビタミンA・C・E」といった、他の守りのビタミンたちとの連携が不可欠です。最強の「栄養ディフェンス」については、こちらの記事で詳しく解説します。

-
💪 筋肉の合成と機能維持
筋肉がスムーズに動くのを助けたり、筋力を維持したりする働きも。転倒予防にもつながります。 -
😌 メンタルの安定
気分の浮き沈みに関わる脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)と関係があると言われ、心の健康にも影響します。
【もっと詳しく!】
「最近、なんだかイライラする…」その原因、もしかしたら栄養不足かも?ストレス社会で戦うあなたの心を軽くするための栄養学については、こちらの記事で詳しく解説しています。

-
✨ 美肌・美髪のサポーター
肌のターンオーバーを正常に保ったり、健康な髪の毛を育む毛包の働きを助けたりと、美容面でも注目されています。
すごくないですか?
骨から免疫、メンタル、美容まで…!ビタミンDが全身の司令塔として、私たちの健康と美容を陰で支えてくれているんですね。
ちょっと豆知識♪ビタミンDの歴史
ビタミンDが発見されたのは、約100年前のこと。
当時、産業革命後のヨーロッパでは、日照不足と大気汚染で子供たちに「くる病」という骨が変形する病気が多発していました。
科学者たちは「タラの肝油を飲むと良くなるぞ!」という事実に着目。
研究を進めた結果、タラの肝油に含まれる未知の栄養素が、この病気を防ぐことを発見したのです。それが、ビタミンA、B、Cに続く4番目のビタミンとして「ビタミンD」と名付けられました。
最初は骨の病気を防ぐ栄養素として知られていましたが、その後の研究で、上で紹介したような全身へのすごい働きが次々と明らかになってきた、というわけなんです。
ビタミンD2とD3、どっちがいいの?
さらに深掘り!
実はビタミンDには、大きく分けて2つの種類があります。
-
ビタミンD2(エルゴカルシフェロール)
-
ビタミンD3(コレカルシフェロール)
「え、なにが違うの?」って思いますよね。
簡単に言うと、由来と体内での働きやすさが違います。
| ビタミンD2 (D2) | ビタミンD3 (D3) | |
| 主な由来 | きのこ類、酵母など | 魚、卵、日光浴 |
| 特徴 | 植物由来 | 動物由来 |
| 働きやすさ | △(やや劣る) | ◎(効率が良い!) |
研究によると、体内でビタミンDレベルを上げる効果は、D2よりもD3の方がパワフルで持続性があることがわかっています。
なので、もし今後サプリメントなどを選ぶ機会があったら、「ビタミンD3」と書かれているものを選ぶのが賢い選択と言えそうですね!この話は第3回の記事で詳しく解説しますのでお楽しみに♪
太陽と皮膚の奇跡!日光でビタミンDが作られるメカニズム
さて、ビタミンDが「太陽のビタミン」と呼ばれる最大の理由、それは日光を浴びることで自分で作れるからでしたよね。
一体どんな仕組みで、太陽の光がビタミンに変わるのでしょうか?
ちょっと理科の授業みたいですが、分かりやすく解説しますね!
ビタミンDを作ってくれるのは「UV-B」だけ!
太陽の光には、目に見える光(可視光線)のほかに、目に見えない「紫外線(UV)」が含まれています。
この紫外線、実は3つのタイプに分かれるんです。
-
UV-A:シワやたるみの原因になる。雲やガラスを通り抜ける。
-
UV-B:日焼けやシミの原因になる。でも、ビタミンDを作ってくれる!
-
UV-C:オゾン層で吸収されるので、地上にはほぼ届かない。
そう、ポイントは「UV-B」!
このUV-Bが私たちの皮膚に当たると、皮膚にあるコレステロールの一種が化学反応を起こして、ビタミンDの元(プレビタミンD3)に変身します。それが体温で温められて、最終的にビタミンD3になるんです。まさに人体の光合成!
「窓際での日光浴」は意味がないってホント?
「それなら、日当たりの良い窓際で過ごせば安心だね!」
そう思ったあなた、残念ながらそこに落とし穴が…!
実は、ビタミンD生成に必要なUV-Bは、窓ガラスをほとんど透過できません。
一方で、シワの原因になるUV-Aはガラスを通り抜けてくるので、窓際にいると「ビタミンDは作られずに、肌老化のリスクだけが高まる」なんてことも…。
ビタミンDを作るためには、必ず屋外で、直接肌に日光を浴びる必要があるんですね。
肌の色で効率が変わる?メラニン色素の役割
肌の色が白い人と濃い人では、ビタミンDの作られやすさが違うって知っていましたか?
肌の色を決める「メラニン色素」には、紫外線から皮膚細胞を守る“天然の日焼け止め”のような役割があります。
肌の色が濃い人は、このメラニン色素が多いということ。
そのため、UV-Bが皮膚の奥に届くのをブロックしやすく、同じ時間日光を浴びても、肌の色が白い人よりビタミンDの生成量が少なくなる傾向があります。
つまり、肌の色が濃いめの方は、意識して少し長めに日光浴をする必要がある、ということです。
【じゃあ、どれくらい浴びればいいの?】日光浴の目安時間
では、1日に必要なビタミンDを作るには、どれくらいの日光浴が必要なのでしょうか?
季節や地域、時間帯によって大きく変わりますが、国が示している目安としては、
「夏場の晴れた日なら、木陰で30分程度」
「冬場の晴れた日なら、顔や手に1時間程度」
と言われています。
「なんだ、それくらいならできそう!」と思いますよね?
…しかし、ここからが現代人にとっての「ワナ」なんです。
【超重要】現代人がビタミンD不足に陥る「5つのワナ」
ここまで読んで、「日光を浴びればいいんでしょ?簡単じゃん!」と思ったかもしれません。
でも、現代の日本には、知らず知らずのうちにビタミンD不足に陥ってしまう“ワナ”がたくさん潜んでいるんです。
最新の研究では、なんと日本人の成人の約8割がビタミンD不足状態にある、という衝撃的なデータも…!
あなたも、このワナにハマっていませんか?
ワナ①:徹底しすぎな紫外線対策
美白や皮膚がん予防のために、紫外線対策はもはや常識ですよね。
日焼け止め、日傘、UVカットのアームカバー…その努力は本当に素晴らしいです!
でも、それがビタミンD生成にとっては大きな壁に。
SPF30以上の日焼け止めを塗ると、皮膚でのビタミンD生成能力は95%以上もカットされると言われています。
美肌とビタミンD、どちらも大事だからこそ、悩ましい問題ですよね。
【もっと詳しく!】
紫外線対策は、外から「塗る」だけでなく、内から「飲む」という新常識も。紫外線に負けない肌を作るための「ビタミンACE」の働きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
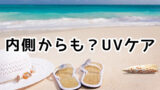
ワナ②:室内中心のライフスタイル
オフィスでのデスクワーク、在宅勤務、休日は家でネットフリックス…。
現代人の生活は、どうしても室内で過ごす時間が長くなりがち。
通勤も電車や車で、太陽の光を浴びる機会はほんのわずか。
これでは、ビタミンDを十分に作ることは難しいですよね。
ワナ③:食生活の変化
本来、日本人は魚をたくさん食べる食文化でした。
サケやサンマ、イワシなどの青魚には、ビタミンDが豊富に含まれています。
でも、食の欧米化が進み、魚を食べる機会が減ってしまった方も多いのではないでしょうか。
食事から摂れる貴重なビタミンD源が、知らず知らずのうちに減っているのかもしれません。
ワナ④:緯度と季節の問題
日本は縦に長い国。住んでいる場所によって、太陽の光の強さ(UV-Bの量)は大きく変わります。
-
✅ 沖縄など南の地域:一年を通してUV-Bが降り注ぐため、比較的ビタミンDを作りやすい。
-
✅ 北海道など北の地域:冬は太陽の角度が低く、UV-Bが地表に届きにくいため、ビタミンDをほとんど作れない。
特に冬場は、日本全国でビタミンD不足に陥りやすくなります。
「冬になると気分が落ち込む」という“冬季うつ”も、このビタミンD不足が関係していると言われているんですよ。
ワナ⑤:加齢による生成能力の低下
悲しいお知らせですが、年齢を重ねると、皮膚でビタミンDを作る能力もだんだん落ちてきてしまいます。
研究によると、70代では20代の約1/4程度しか作れなくなるとも…。
高齢者の方が骨粗しょう症になりやすかったり、転倒しやすかったりする背景には、このビタミンD生成能力の低下も大きく関わっているのです。
まとめ:太陽の恵みを上手に受け取ろう!
シリーズ第1回、お疲れ様でした!
最後に、今日の内容をサクッとおさらいしましょう。
-
✅ ビタミンDはホルモンのような働きで、骨・免疫・メンタルなど全身をサポートする司令塔!
-
✅ 日光の「UV-B」を直接肌に浴びることで、体内で作ることができる。
-
✅ 現代人は「紫外線対策」「室内生活」「食生活」「季節」「加齢」という5つのワナで不足しがち。
-
✅ 最新の研究では、日本人の多くがビタミンD不足状態!
ビタミンDのすごさと、私たちがなぜ不足しやすいのか、お分かりいただけたでしょうか?
「もしかして、私も不足してるかも…」とドキッとした方もいるかもしれませんね。
★★★ 次回予告 ★★★
では、実際にビタミンDが不足すると、私たちの心と体にはどんなサインが現れるのでしょうか?
そして、健康や美容のためには、1日にどれくらいの量が必要なのでしょうか?
次回の【第2回:実践編】では、
【ビタミンD不足の症状】免疫力低下・うつは危険サイン?セルフチェックと必要量
というテーマで、さらに深く掘り下げていきます!
あなたの体の声に耳を傾けるセルフチェックリストもご用意するので、ぜひお見逃しなく♪
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
次の記事でまたお会いできるのを楽しみにしています✨
![]()



